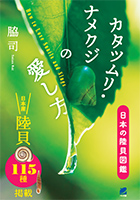寄生虫は気持ち悪いと思われることがほとんどだ。
しかも「あいつは寄生虫みたいだ」という言葉に尊敬の気持ちは微塵もない。
そう、寄生虫はこの世の中でかなり厳しいポジションにいるわけなのだが、
あまりにも多くの寄生虫が私たちのそばにいるので無視をするわけにもいかない。
というか、自然の中に出かけて行き、よく見てみるとこれが実に面白いのだ。

著者プロフィール
脇 司(わき・つかさ)
1983年生まれ。2014年東京大学農学生命研究科修了。博士(農学)。日本学術振興会特別研究員、済州大学校博士研究員、2015年公益財団法人目黒寄生虫館研究員を経て、2019年から東邦大学理学部生命圏環境科学科講師、2022年4月から同大准教授。貝類の寄生生物をはじめ広く寄生虫を研究中。単著に『カタツムリ・ナメクジの愛し方:日本の陸貝図鑑』(ベレ出版)がある。
あなたのそばに寄生虫
第8話
サカマキガイの逆襲
文と写真 脇 司
最初は「まあ、あまり気にしなくていいや」と受け入れてきたものが、あとになって実は「おおごと」だったと気づくこと、ないだろうか。締切りが1年後とかにある重い頼まれごとや(締め切り直前に後悔)、寝る前に食べてしまったカップラーメン(翌朝に胃もたれ)など、人によっていろいろな経験があると思う。
今回は、サカマキガイの話になる。この貝は北米原産の外来種であるにもかかわらず、目立った悪さをしてこなかったので、人畜無害な貝として注目されてこなかった。しかし、2024年になって、海外由来の複数の寄生虫の感染源として、日本に君臨してきたことが分かってしまった。
アクアリウムでおなじみ、サカマキガイ
サカマキガイは、1cmに満たない大きさの北米原産の淡水貝で(図1)、観賞魚用の水草が輸入される際に一緒にくっついて日本に来たと考えられている。皆さんの家や教室の水槽にも、この貝が紛れているかもしれない。熱帯魚屋さんに行けば、水槽の中に小さなサカマキガイがのそのそと歩いている様子をきっと観察できるはずだ。
サカマキガイは、水草と一緒に川に捨てられたり、あるいは魚の飼育水が外に流されるときに一緒に外に出たりして、野外に定着してしまったのだと思われる。日本の野外では、1950年ごろからこの貝が見つかったとの記録がある。今やこの貝は日本全国に広がっており、沼や池などのあまり水の流れが強くない場所を特に好んで生活している。日本の淡水でもっともメジャーな貝の一つと言えるだろう。

図1. サカマキガイ。殻サイズは1cmもない小型の淡水巻貝だ。水草などに紛れて水槽に入り込んでくるので、あなたの部屋の水槽にもいるかもしれない。逆巻き(さかまき)の名の通り、殻の巻きが左巻き(殻の口が向かって左側にある)なのが特徴だ(写真:安齋榮里子)。
外来種とはいえ、サカマキガイは水草や稲を食い荒らすこともなく、日本の生き物を直接攻撃することもなく、毒があるわけでもなく、大量発生することもなく、そこまで気持ちが悪いわけでもなく…悪さをしているのかしていないのかはっきりしない、影の薄い貝だった。人間サイドにも積極的にこの貝を駆除しようという動きはなく、なんとなくスルーされ続けてきた。しかし、サカマキガイは「ヘビ・カエルにつく海外由来の寄生虫の感染源」になっていることが、2024年の僕らの研究によって明らかになった。
日本のヘビの敵? ヘビクチグロ吸虫
ヘビクチグロ吸虫(学名:Ochetosoma elongatum)は、吸虫と呼ばれる寄生虫のひとつで、北米が原産地だ。日本では関東に侵入しており、外来種の寄生虫となる。この吸虫は、シマヘビなどの日本在来ヘビの口の中をはじめ(図2)、体の中のいろいろな臓器に寄生する。ちなみに、この寄生虫の仲間を「顎口虫」として紹介するサイトが散見されるけれど、顎口虫は全然違う分類群の寄生虫で、ヘビクチグロ吸虫とは全く異なる存在だ。

図2 A. シマヘビの口の中に寄生したヘビクチグロ吸虫(矢印)の成虫。B.ヘビクチグロ吸虫の顕微鏡写真。体長は数mmもない程度の小さな吸虫だ(写真:瀬尾栄滋)。
北米では、この吸虫は北米在来のガーターヘビなどに付くが、そのヘビに対する病害性はおそらく低いと考えられている。これは、この吸虫とガーターヘビが地球の長い歴史の中で共存してきた過程で、病害性の高すぎる吸虫は宿主を殺すことで一緒に消滅し、病気に弱すぎるガーターヘビもまた寄生を受けて消滅してきたからだ。つまり、生き残った「病害性の高くない吸虫」と、「そこそこ病気に強い宿主のヘビ」の間でなあなあの寄生関係を長い時間をかけて築き上げてきたのだ。
一方で、日本には、ヘビクチグロ吸虫をはじめとして、口の中にへばりつく寄生虫は元々いなかった。この吸虫は日本で発見されたばかりで調査が不十分であり、日本のヘビに対する病害性は分かっていないが、この吸虫に感染した日本在来ヘビに唾液の異常分泌が確認されている。おそらく、日本のヘビに対する病害性は、低くはないものと想像される。日本のヘビの感染予防のためには、この吸虫の感染ルートを明らかにする必要がある。そこで、僕たちはこの吸虫の日本での生活史を調べることにした。
北米では、ヘビに寄生した虫卵が淡水の貝に寄生して、そこからカエルに感染がまわって、そのカエルを食べたヘビが感染する。そこで、日本のいろいろな貝やカエルにこの吸虫の幼虫がついてないか調べていった。今のところは日本にいるカエルから幼虫が見つかっていないが、関東に侵入したサカマキガイからは、この吸虫の幼虫が発見されている。
つまり、サカマキガイに感染した吸虫がセルカリア幼虫という遊泳性の幼虫を水中に放出し、それが日本にいるカエルのいずれかに感染し、それを食べたヘビがこの吸虫に感染してしまうのだ(図3)。ヘビクチグロ吸虫は北米原産なので、原産地が同じ北米のサカマキガイを感染源として利用していた、ということになる。日本原産の貝にはうまく感染できないようだ。

図3. 北米原産の寄生虫「ヘビクチグロ吸虫」の日本での生活史。ヘビに寄生した成虫が産卵し、虫卵が水に入ると、続いてサカマキガイに食べられて感染する。貝の体内ではスポロシスト幼虫ができ、その内部では多数のセルカリア幼虫ができる。やがてセルカリア幼虫は水中に出て遊泳し、カエルに感染してメタセルカリア幼虫となる。その感染カエルがヘビに食べられて感染する。日本で宿主となるカエルは現在不明(イラスト:脇 司)。
日本へ定着できた理由とは?
この吸虫が日本へ侵入できた経緯を調べていくと、サカマキガイがあらかじめ日本に定着していたことが、ヘビクチグロ吸虫が日本に定着できた要因になっていたことが分かってきた。
日本では、1973年に日本の爬虫類の寄生虫リストが作られているが、このリストには、ヘビクチグロ吸虫は載っていない。したがって、この吸虫は1970年ごろより後に日本に入ったと考えられる。また、この吸虫の日本への侵入経路は、この吸虫に感染したサカマキガイ、カエル、ヘビのいずれかが日本に輸入されたためと思われる。僕は以下の理由から、サカマキガイか北米産のヘビのどちらかあるいは両方が、吸虫の侵入経路と考えている(図4)。

図4. ヘビクチグロ吸虫の日本への2通りの侵入経路。ヘビクチグロ吸虫は、北米原産のサカマキガイが日本に定着した1950年ごろから、日本に定着可能になったと思われる。今のところ、①と②の2通りの侵入経路があると思われる。①1990年代から観賞魚ブーム到来。水草が沢山輸入され、それにくっついて感染サカマキガイが日本に来た。その感染貝が野外に出たり、あるいは貝から遊出したセルカリア幼虫が野外に出ることで、ヘビクチグロ吸虫が野外に出て定着した。②2000年代に北米産の野生ヘビが繰り返し輸入され、やがて感染ヘビが日本に侵入。そのヘビの死体や、虫卵のついた飼育資材などが野外に捨てられ、虫卵から野外のサカマキガイに感染成立(イラスト:脇 司)。
まず、サカマキガイは、1950年ごろから日本の野外で確認され始めている。この時期は、爬虫類の寄生虫リストが作られた1973年よりも前なので、この時にはまだ吸虫は侵入していない。続いて1990年ごろになると、日本で観賞魚ブームが始まった。このとき、海外からいろいろなアクアリウム資材が輸入され、水草の輸入量も増えただろうから、日本にはたくさんのサカマキガイが入ってきたと思われる。このサカマキガイの中に、感染サカマキガイが紛れ込んだのではなかろうか、と僕は考えている。そして、感染サカマキガイが外に逃げたり、水槽の中でサカマキガイから出てきたセルカリア幼虫が水と一緒に野外に流されたりして、吸虫が野外に出たのかもしれない。次にヘビだが、日本で北米原産のヘビが野外に逃げて定着した事例は見当たらない。一方で、エキゾチックペットの人気が1990年代から高まっていたようで、2005年以降には北米からのヘビ類の輸入重量が増加している。その輸入ヘビの中に北米産の感染ヘビが混じっており、それが日本への侵入経路になったのかもしれない。たとえば、その感染ヘビが死んだときに飼育者が死体を吸虫ごと野外に投棄したり、あるいは虫卵の混じったヘビの糞のついた飼育床材などを野外に捨ててしまえば、この吸虫の卵が外に出ることになる。虫卵が野外のサカマキガイに感染すれば、この吸虫は野外で定着できることになる。
カエルについては、この吸虫の侵入経路ではないと僕は思っている。北米では、ヘビクチグロ吸虫の幼虫が、北米原産の(現地では在来種)ウシガエルなどから見つかっている。一方で、ウシガエルが北米から日本に来たのは1918年の一回きりとなる。この年より後に、ウシガエルをはじめとした北米のカエルが日本に入ってきた記録はない。1918年には、そもそもサカマキガイが日本にいないので、仮にこのときに輸入されたウシガエルに虫がついていたとしても、日本で生活史が成立せず定着不可能だ。
いずれにせよ、この吸虫が日本で定着できたのには、サカマキガイが日本に沢山いたからだと思われる。これまで無害だと信じられてきたサカマキガイだが、実は日本にヘビの新しい病気を定着させる下地作りに貢献していたことになる。現在、ヘビクチグロ吸虫は、関東にしか分布していないが、サカマキガイは全国的に分布している。ウシガエルを含むカエルやヘビも、日本に広く自然分布している。このため、感染している可能性のあるサカマキガイ、カエル、そしてヘビを人の手で捕まえて、別の場所に逃がしてしまうと、この吸虫の感染域を広げてしまうことになる。野生の生き物を人の手で別の場所に移してしまうことは、寄生虫学者の視点からみれば、日本の生態系を確実に破壊する行為であり、絶対にやめるべきだと考えている。
北米から生活史をまるごと日本に持ち込んだ寄生虫
サカマキガイにはもう一件、北米から日本に寄生虫を持ち込んだ事例がある。
日本に定着した北米原産のウシガエルには、北米原産の吸虫「ウシガエル斜睾吸虫(学名:Glypthelmins quieta)」の成虫が寄生する(図5)。宿主のカエルも寄生虫も北米原産だ。
この吸虫は、北米では生活史が明らかになっている。まず、成虫がウシガエルに寄生し、消化管で産卵する。ウシガエルの糞に虫卵が混じった虫卵が水中に出て、淡水貝に感染する。感染した淡水貝からは遊泳性のセルカリア幼虫が放出され、ウシガエルの表皮に寄生してメタセルカリア幼虫になる。ウシガエルは脱皮して自分の皮を食べるが、この時に幼虫を一緒に飲み込んで感染が成立する。

図5. 北米原産の寄生虫「ウシガエル
斜睾吸虫」(撮影:齊藤佳希)。
一方で、日本ではウシガエルから成虫が記録されていただけであり、幼虫のつく貝(中間宿主)は分かっていなかった。そこで僕たちが調べたところ、サカマキガイが中間宿主になっていることが明らかになった。この結果から、北米原産のこの吸虫は、同じく北米原産のウシガエルとサカマキガイを利用して、日本で生活していることが明らかになった(図6)。北米から、寄生虫とその生活史が丸ごと日本に持ち込まれたことになる。人に例えると、自宅や新聞、ネット環境などのインフラまで丸ごと移動して引っ越してきた、ということになるだろうか?斜睾吸虫」(撮影:齊藤佳希)。

図6. 北米原産の寄生虫「ウシガエル斜睾吸虫」の日本での生活史。ウシガエルの消化管に寄生した成虫は産卵し、虫卵が宿主の糞とともに外にでる。虫卵が淡水貝のサカマキガイに感染し、その体内でスポロシスト幼虫になる。スポロシスト幼虫の内部では多数のセルカリア幼虫ができ、貝の外にでる。セルカリア幼虫は水中を遊泳し、ウシガエルの表皮に感染してメタセルカリアとなる。ウシガエルは脱皮時に自分の皮を食べて経口感染する(イラスト:脇 司)。
日本では、1975年にカエルを含む両生類の寄生虫リストが作られていたが、この吸虫は載っていない。その後、2007年~2011年に行われた調査で、この吸虫が日本で初めてウシガエルから記録されている。したがって、この吸虫は1970年代~2000年代の間のどこかで日本に侵入して定着したことになる。すでに説明した通り、ウシガエルは1918年に北米から初めて導入され、その後は日本に入っていない。一方でサカマキガイは、1950年ごろから日本の野外で見つかり始め、その後の鑑賞用の輸入水草などに付いて海外から繰り返し日本に入ってきたと思われる。特に、1990年代以降の観賞魚ブームの時にサカマキガイがたくさん持ち込まれ、その中に感染サカマキガイが入ったのではないだろうか(図7)。いずれにせよ、感染サカマキガイが日本に入った時には、日本には野生のサカマキガイとウシガエルがたくさんいたので、この吸虫はすぐに日本で定着できたと思われる。

図7. 北米原産の外来寄生虫「ウシガエル斜睾吸虫」の、本研究で推定された日本への導入経緯。日本では、1918年にウシガエルが北米から持ち込まれた。サカマキガイは、1950年ごろ日本に定着し始めたと考えられる。サカマキガイは水草の輸入に付随して繰り返し日本国内に侵入していたが、おそらく1990年代以降の観賞魚ブームの時に、感染サカマキガイが日本に侵入し、野外のウシガエルとサカマキガイを利用して日本に定着したのではないだろうか(イラスト:脇 司)。
こうして、日本に入ってきた北米産の吸虫2種を根絶するには、サカマキガイを徹底的に駆除すればよいことが分かった。しかし、この貝はすでに日本の田んぼ、水路、池、川に広く定着しており、根絶は不可能だ。このように、生態系にクリティカルな影響を与えていないように見えた外来種サカマキガイは、海外の病気が侵入したときに、その温床になるポテンシャルを秘めていた。サカマキガイと北米の吸虫2種の事例は、どんな無害そうに見える生き物でも、その地域の外から持ち込んではいけない、という警鐘なのだろう。
【引用文献】
1.Ansai, E., Nitta, M., Saito, T., Kojima, Y., & Waki, T. (2024). The first intermediate host of the invasive frog trematode Glypthelmins quieta in Japan. Diseases of Aquatic Organisms, 159, 9-14.
2.Seo, H., Ansai, E., Sase, T., Saito, T., Takano, T., Kojima, Y., & Waki, T. (2024). Introduction of a snake trematode of the genus Ochetosoma in eastern Japan. Parasitology International, 103, 102947.