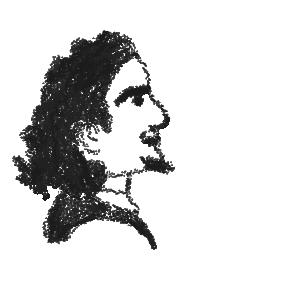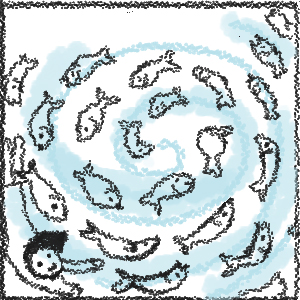知の巨人アリストテレス、分類学の父リンネ、
古生物学の創始者キュヴィエと連なる、自然に対する知識を体系化する博物学は、
19世紀半ばにダーウィンとウォーレスの進化論に到達した。
事実に基づき、歴代の学者たちが打ち立てた仮説の数々を丁寧に読み解きながら、
分子系統学の登場で新たな時代を迎えた“進化学の現在”までを追う。

著者プロフィール
長谷川政美(はせがわ まさみ)
1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)『新図説 動物の起源と進化―書きかえられた系統樹』(八坂書房)など多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターは全編監修を務める。

進化の歴史
ー時間と空間が織りなす生き物のタペストリー
第7話
なぜ多様な種が進化したか?
文と写真 長谷川政美
◎自然選択
なぜ地球上には多様な生物が存在するのであろうか。ダーウィンは「自然選択」のせいだと考えた。『種の起源』の原著のタイトルは、「自然選択すなわち存続をめぐる争いにおいて有利なものが保存されることによる種の起源」であるが、そのなかの「存続をめぐる争い」が重要である。
1つがいの動物が4匹の子供を残すとする。この子供がすべて生き残ってまた同じように子供を残し続けるとすると、世代ごとに個体数が倍になることになる。n世代後の個体数は、2をn回掛け合わせて、2nとなるから、10世代後には210≈103、50世代後には250≈1015 、100世代後には2100≈1030と幾何級数的に増えるので、またたく間に天文学的な数になる。ところが実際にはこんなことは起らない。資源が限られているため、生まれた子供のなかで次世代に子供を残せる個体は限られるのである。
ダーウィンは生存に有利な特徴をもった個体が、そのような特徴をもたない個体よりも平均して多くの子供を残すと考えた。これが「自然選択」である。
このような存続をめぐる争いは、異なる種の間でも起こるが、種内での競争が一番激烈である。同じ種に属する個体は、必要とする環境や食べ物が共通だからである。従って、少しでも違った資源を利用できるように進化すれば、個体数を増やすことができる。
ダーウィンは多様性の進化も、もとをただせば自然選択によると考えた。生物の多様性が増せば、環境の多様性も増すので、ますます多様な種の進化が可能になるのだ。
◎地球上の生物種数
リンネ以来、博物学者は極地から熱帯まで、また高山から深海まで地球上のあらゆる場所でさまざまな生物を記載し、それらを分類してきた。Catalogue of Life: 2017 Annual Checklistというインターネットのサイトは、すべての種を登録することを目指しているが、そこには現在1,664,506の現生種と49,346 の絶滅種が登録されている。これは、知られている種のおよそ3/4だというので、これまでに知られている現生種は、およそ220万種ということになる。しかし現在でも毎年新しい種が発見されているので、実際の種数はこれよりもはるかに多いはずである。
まだ記載されていない種がどれだけ存在しているかは難しい問題であるが、2011年にカナダのカミロ・モラらが行った推測によると、細菌類を除いた真核生物は、およそ870万種に達するという。これらのなかには、ヒトに知られる前にひっそりと絶滅していく種もたくさん含まれている。
ダーウィンが壮大なものがあると形容したように、1つの共通祖先からこのようにさまざまに分化した膨大な数の種を、1本の“生命の樹”のなかに位置づけることが、系統学の役割である。“生命の樹”のなかに位置づけることが、その種がどのような進化の歴史をたどって生まれたかについて、研究する出発点になる。
ダーウィン以来、生物学者は1つひとつの種を“生命の樹”のなかに位置づける作業をコツコツと進めてきたが、その際の手掛かりはそれぞれの種がもつ形態的な特徴や生理的な特徴であった。互いに似たような特徴をもっている種は、生命の樹のなかで近い位置を占めると考えられるのだ。しかし、問題は簡単ではない。同じような特徴が、別々の系統で収斂的に進化することがあるからだ。ダーウィンもそのことには気がついていた。
◎収斂進化
『種の起源』の「学説の難点」と題した章でダーウィンは、一見自分の説には不都合と思われる事柄を並べ、ひとつひとつ反論している。そのなかに、次のような文章がある(第6章、八杉竜一訳、岩波書店)。
もしも電気器官がそれをそなえた太古の祖先から遺伝されたものであるとするなら、すべての電気魚が相互に特別の関係をもつことを予期してもよいことになろう。地質学も、以前には大部分の魚類が発電器官をもっていて、その変化した子孫の大部分においてそれが失われた、と信じさせることは、まったくないのである。……二人の人間がときにまったくおなじ発明を思いつくことがあるのとほぼ同様に、自然選択がそれぞれの生物の利益のためにはたらき相似的な変異を利用することによって、共通の祖先からの遺伝による共通な構造をあまりもたない二個の生物で二個の部分をひじょうによく似た方式で変化させることがある、と信ずることに、私はかたむいている。
つまり、「収斂進化」ということである。ここで引用した文章は1859年に出版された『種の起源』の初版のものであるが、ダーウィンはその後もこの問題に取り組み、第6版では、同じように電気を発生させる電気ウナギと電気ナマズで発電器官の構造に大きな違いがあることを示し、収斂的に進化したと思われる証拠を挙げている。ダーウィンが「二人の人間がときにまったくおなじ発明を思いつくことがある」と述べているのは、前年にウォーレスが自分とは独立に自然選択説に到達したことを念頭に置いたものであろう。
図7-1の左はアゴヒゲハチドリというハチドリ、右はホシホウジャクというスズメガである。鳥類と昆虫というまったくかけ離れた動物であるが、どちらも高速ではばたいて、空中で静止しながら(これをホバリングという)、花の蜜を吸う。ウォーレスが1848年にアマゾンに出掛けたとき、最初は友人のヘンリー・ベイツ Henry Bates(1825—1892)が一緒だった。後に2人は別々に行動するようになるが、ベイツはアマゾンでハチドリの標本を得ようとして、しばしばよく似ているスズメガを撃ち落としたという。もちろん、標本を見てこの2つを混同することはないが、一見非常によく似ていることは確かである。


図7-2 ベイツ型擬態.左:トンボマダラ(トンボマダラ科)、右:トンボコバネシロチョウ(シロチョウ科)(倉敷市自然史博物館所蔵標本)。どちらも南アメリカのチョウ。
図7-3aは、20世紀に絶滅したオーストラリアのフクロオオカミである。この動物は、カンガルーと同じ有袋類だが、真獣類のオオカミ(図7-3b)とよく似ているために、“オオカミ”という名前がついている。オーストラリアの有袋類のなかには、ほかにも真獣類のネコ、モモンガ、モグラなどに似たものが、収斂的に進化している。
ダーウィンが電気ナマズと電気ウナギが別々に進化したと考えたように、有袋類の“オオカミ”には有袋類に特有な特徴があるので、真獣類のオオカミと間違うことはない。これまで取り上げたほかの収斂もすべて、詳しく調べれば近縁だからではなくて、収斂の結果であることが分かる。
しかし、もっと近縁な真獣類のなかの2つの系統で収斂進化が起った場合には、そのような共通の特徴が祖先を共有するためなのか、収斂進化によるものなのかを判定することが難しくなる。


図7-3 有袋類と真獣類の間の収斂。(a)有袋類のフクロオオカミ Thylacinus cynocephalus、(b)真獣類のオオカミCanis lupus。
図7-4に互いに似た特徴をもった2種の真獣類が並んで示されている。左のaはインドハリネズミ、右のbはマダガスカル固有のハリテンレックである。どちらも体毛が針状になっていて、敵に襲われると写真のように丸まって、身を守る。ハリネズミはモグラやトガリネズミに近いということで食虫目に分類されていたので、これとよく似たハリテンレックも当然食虫目に属するものだと考えられてきた。


図7-4 真獣類のなかの収斂。(a)インドハリネズミ Paraechinus microps、(b)ハリテンレック Setifer setosus。
◎分子進化の中立説
このように収斂進化が起るので、2つの生物種で似たような特徴が見られても、それが共通祖先の特徴を受け継いだからなのか、あるいは別々の系統で同じような特徴が収斂的に進化したためなのかを判別しなければならない。
ところが、ハリネズミとハリテンレックの例で見られるように、形態形質だけに頼る方法で収斂進化であると判定するのは難しいことが多い。形態的な特徴には、生きていく上で有利になるように適応したものが多いので、似た環境で似たような生活をしている生物の間には似た特徴が収斂的に進化しやすいのである。
ダーウィンもこのことには気がついていた。彼は、現在は機能を失った痕跡器官は種の由来を明らかにする手掛かりとして有効だと述べている。痕跡器官には適応的な自然選択は働かないので、系統が離れるに従って違いが大きくなるような進化だけで、収斂は起らないからである。現在の系統学において、生命の樹を構築するにあたってもっぱら用いられるDNAにもこれに似た性質がある。
それが、木村資生(1924–1994)が提唱した「分子進化の中立説」である。形質の違いによって環境への適応など生きのびる上(厳密には子孫を残す能力)で差があれば、より適応度が高い形質が選ばれ、次第に種が変化していくというのが、自然選択説である。より適応した形質が選ばれることを「正の自然選択」という。それに対して中立説によると、DNAのレベルでは適応度に差がないような中立的な変異が選択されて進化することが多いという。
多くの生物では、母親と父親から一揃いずつゲノムをもらうが(合わせて2倍体という)、ヒトの場合は一揃いのゲノムDNAはおよそ3億個の塩基から成る。この3億個のDNA形質のほとんどは、中立的に進化するということである。
木村の中立説が提唱される以前は、DNAのレベルであっても、進化の過程でDNA塩基が別の塩基に置き換わるのは、より適応度が高いものが選択された結果であると考えられてきた。木村は、DNAの進化においては、そのような「正の自然選択」が働くこともあるが、大部分は適応という観点からは良くも悪くもない中立的な変異が機会的に(偶然)選ばれた結果である、と主張した。
突然変異で生ずる変異のなかには、適応度を低める有害なものもあるので、当然そのような変異は取り除かれる。そのことを「負の自然選択」という。中立説によると、DNAレベルの変異のうち、負の自然選択で取り除かれる変異を除いたものは大部分が中立的なものであり、それらが機会的に集団に広まって固定するという。
負の自然選択という考えは、ダーウィン以前からあった。創造主によって造られた種は完璧なデザインに基づくものであるはずだから、それから外れた変異は取り除かれるはずだというわけである。そのような考えのもとでは、進化は起りえないことになる。それに対してダーウィン(とウォーレス)は、正の自然選択によって適応的な進化が進むと考えたわけである。中立説はある意味でダーウィン以前からあった「負の自然選択」という考えの復活ともいえるが、「正の自然選択」を否定するわけではなく、あくまでもDNAレベルでは中立的な変化が多いということを主張するものである。
*もっと「進化」を詳しく知りたい人に最適の本:
長谷川政美著『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』 (ベレ出版)。 本書は当サイトで連載していた「僕たちの祖先をめぐる15億年の旅」を加筆修正および系統樹図を全て作り直して一冊にまとめたものです。カラー図版600点掲載。
扉絵:小田 隆
ブックデザイン:坂野 徹