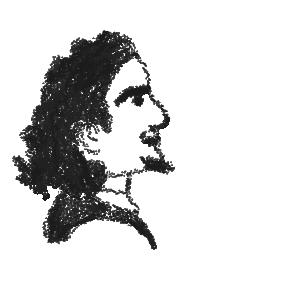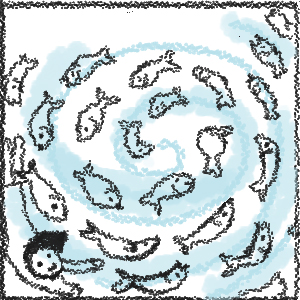知の巨人アリストテレス、分類学の父リンネ、
古生物学の創始者キュヴィエと連なる、自然に対する知識を体系化する博物学は、
19世紀半ばにダーウィンとウォーレスの進化論に到達した。
事実に基づき、歴代の学者たちが打ち立てた仮説の数々を丁寧に読み解きながら、
分子系統学の登場で新たな時代を迎えた“進化学の現在”までを追う。

著者プロフィール
長谷川政美(はせがわ まさみ)
1944年生まれ。進化生物学者。統計数理研究所名誉教授。総合研究大学院大学名誉教授。理学博士(東京大学)。著書に『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』(ベレ出版)『分子系統学』(岸野洋久氏との共著)『DNAに刻まれたヒトの歴史』(共に岩波書店)『新図説 動物の起源と進化―書きかえられた系統樹』(八坂書房)など多数。1993年に日本科学読物賞、1999年に日本遺伝学会木原賞、2005年に日本進化学会賞・木村資生記念学術賞など受賞歴多数。進化が一目でわかる「系統樹マンダラ」シリーズ・ポスターは全編監修を務める。

進化の歴史
ー時間と空間が織りなす生き物のタペストリー
第5話
偶然性の重視
文と写真 長谷川政美
◎ダーウィンの「自然選択説」
19世紀初頭までの博物学者の一般的な考え方によれば、生物の複雑なかたちや環境への適応こそ、創造主の存在の証拠であった。複雑な時計ができるためには、それをデザインする人間が必要なように、複雑な生物が生まれるためには創造主によるデザインが必要であるという考えである。これを「デザイン論」という。
一方、自然の階段を上るという進化の考えは、あらかじめ決められたゴールに到達するような意図を想定したもので、「目的論」と呼ばれる。目的をもたない自然が、生物の複雑な構造を作り出せるはずがない、という考えである。
アリストテレスは、次のように述べている。「道具はすべて何かのためにあり、体の諸部分は各々何かのためにあり、「それのために」という目的はある種の活動であるから、全体としての体も、ある全き活動のために構成されているのは明らかである」。ダーウィンが学生時代に魅せられた時計製作者の比喩が出てくるウィアム・ペイリーの『自然神学』は、アリストテレスの流れをくむものである。
ダーウィンの「自然選択説」は、このようなデザイン論や目的論を否定する。彼は、集団中に偶然に生ずるたくさんの変異のなかからさまざまな環境によりよく適応した個体が生き残ることによって、進化が起るとした。多様な生物が進化する仕組みとして自然選択説を考えたのであった。目的論に頼らなくても、ランダムに起きる変異のなかからより適応した個体が選択されることによって、結果的に進化に方向性を与えられるのだ。無目的な偶然的な現象によって、生物の合目的性がもたらされるというこの考えは、画期的なものであった。
ダーウィンのこのような考えには、近代統計学の基礎を築いたベルギーのアドルフ・ケトレー Adolphe Quetelet (1796-1874)の影響があるという。ケトレーは、個人間にばらつきがあっても、最もしばしば観察されるのは「平均」であり、大量の観察は法則をもたらすというものである。これは現在でも統計学の発想であるが、ダーウィンの自然選択説は、ばらつきのあるたくさんの個体が、長い時間をかけてある法則性をもった変化を遂げるというものである。
ニュートン力学の決定論的世界像は、ダーウィンが生きた19世紀の西洋社会においても支配的であった。そのような世界像は、20世紀に入って量子力学が現れ、そのなかで不確定性原理によって覆された。物理学では19世紀後半のボルツマンの熱力学にその兆候を見ることができるが、生物学の世界におけるダーウィンにその先駆けを見ることができる。
◎集団対象の考え
ダーウィンが踏み出した大きな一歩が、独自性をもつ個体から成る変化し得る集団(個体群)という概念であった。生物集団中の個体ごとの変異こそ実在のものであり、平均は統計的抽象に過ぎないという考えである。個体の重要性の発見こそがまさしく、自然選択説の要となった。集団対象の考えは、個体の独自性と進化における個の役割に重点を置く。
ある集団中のすべての個体が独自性をもつということは、それらがすべての点で互いに異なるという意味ではない。ほとんどの点では同じだが、どの個体にも独自の特徴の組み合わせがあり、特徴の一部は他の個体には見られないということである。このことによって、自然選択による進化が可能になるのである。
ダーウィンが個体間の変異に関心をもつようになったのは、1837年頃に図4-1のような最初の「生命の樹」をノートに記した後、8年間ほど蔓脚類の研究に専念していた間だったと言われている。
蔓脚類は、図1-3bや図2-2のラマルクの枝分かれ図にも出てきたが、フジツボの仲間である。この動物は一見、貝のようにも見え、ラマルクの時代では軟体動物と考えられていた。ところが、1830年頃に甲殻類の幼生と同じような水中を遊泳する幼生が発見されて、甲殻類であることが分かったのである。ダーウィンはこの蔓脚類の分類学的な研究を行なった。たくさんの種の、それぞれの種ごとの膨大な数の標本を詳しく調べた結果、次のような結論に達したのである。
「どの一つの種についても、どれか特定の部分あるいは器官に、形あるいは構造が絶対的に不変なものを見つけられる見込みはない。」
それまでの分類学者にとっては、種内の変異は分類の作業を難しくするやっかいなものに過ぎなかった。エルンスト・マイヤー Ernst Mayr (1904 – 2005)よると、このようなものの見方は、イデア論と呼ばれるプラトン以来の西洋文明の伝統だという。洞窟の比喩として知られたプラトンの言葉がある:「われわれは生まれてからずっと洞窟のなかに閉じ込められているようなものである。われわれが世界の現象として見ているものは、火に照らされた外界にある実在の影が、洞窟の壁に投じられたものにすぎない。真の実在そのものを見ることは、われわれには決してできないのだ。」
変異とは、真の実在が、ゆらゆら揺れる不完全な影となってあらわれたものに過ぎないというわけである。創造主のデザインということであれば、種とはそのデザインつまり原型によって定義されるものであり、個体変異はその理想つまりイデアからの逸脱に過ぎず、特に重要なものとは見なされない。個体という具体的な事象の背後にある本質(イデア)を見抜くことが重要だった。分類学者の仕事は、変異によって隠されているイデアをできる限り明らかにすることだと考えられていたのだ。
ダーウィンはこれとは逆に、それまで顧みられることのなかった個体変異こそ、生物が進化する上での原動力になっていることを認識したのである。個体間の変異とそれに対して働く自然選択があれば、生物は自律的に多様な種を生み出すことができるという。彼にとっては、観念論的な議論ではなく、事実に基づく議論がすべてであった。彼の『種の起原』では、最初の第1章と第2章がそれぞれ、「飼育栽培のもとでの変異」と「自然のもとでの変異」というふうに、変異をテーマにした議論にあてられている。
ダーウィンは遺伝のメカニズムを知らなかったが、彼の死後、メンデル遺伝学の再発見を経て、集団遺伝学に基礎を置いた現代の進化学に発展していくことになる。現在では、進化とは、時間の経過による集団の遺伝的構成の変化としてとらえられるようになってきた。
◎進化は退化も含む
蔓脚類の研究は、ほかにも副産物をもたらした。蔓脚類のなかにエボシガイというほかの蔓脚類の体内に寄生することで保護されているプロテオレパス Proteolepas bivincta がいる。一般に、蔓脚類の殻は、大きな神経と筋肉を備え、巨大に発達した頭部前方の重要な3つの体節でできている。ところが寄生性で宿主に守られているプロテオレパスでは頭部前方の部位全体が委縮して痕跡器官となっている。ダーウィンは、この動物が寄生性になった時点で不要になった構造を節約することは、次世代以降の個体にとって決定的な利益になったに違いないと考えた。
実は現在では、プロテオレパスは蔓脚類ではなく、同じ甲殻類のなかの等脚類であるとされているので、上のダーウィンの議論はそのままでは成り立たない。それでも寄生生活を始めて、器官が退化した例はたくさん知られている。そのことは、ダーウィン以前の進化学者が考えたように、生物の進化はある方向を目指して階段を登るように進むものではなく、その時々の状況で有利な形質が選ばれるという自然選択の考えの正しさを示している。さらにダーウィンは、一般に痕跡器官は変わりやすいという。彼は、そうした器官はすでに不要になったためであり、そのせいで自然選択には構造の変異を精査する力がないからだと指摘する。
ダーウィンの『種の起源』には、飛べなくなった鳥の例が挙げられている。ダチョウは大陸にすんでいて多くの危険にさらされているが、飛んで逃げることができない。しかし、脚で敵にキックを与えることで身を守ることができる。キックの効果は、体が大きくなるほど高まるので、自然選択によって体が次第に大きくなり、飛ぶよりも走ることが多くなり、ついに飛べなくなったのだろうという。空を飛ぶ能力は、敵から逃れるには役に立つが、コストがかかるため、その能力なしでやっていけるならば失うことがあるということだ。
ダーウィンはまた、大西洋マデイラ島の甲虫が翅を退化させて飛べなくなったことも自然選択で説明する。風の強いこの島では、よほど強力な飛翔力をもたない限り海に吹き飛ばされてしまうので、むしろ翅を退化させたほうがこの島では有利だったのではないかという。
◎不完全な適応
創造主によって種が作られたのであれば、それぞれの種はその生息環境に完全に適応していることが期待される。ところが、実際にはそのようには見えない生物種がたくさんいる。
例えば、カモなどの水鳥には、泳ぐための水かきが発達している。ところが、カモと同じように脚で水を蹴って泳ぐバンには水かきがまったくない(図5-1a、b)。


ダーウィンは、バンの祖先が水鳥としての生活を始めてまだ日が浅いために、形態的な進化が追いついていないためであろうと考えた。「習性はそれに応じた構造の変化をともなわずに。変化している」と述べている。バンはツル目クイナ科に属する鳥で、水辺に生息し、よく泳ぐ。しかし、水上を泳ぐときには頭を前後に揺らし、少しぎこちない。図5-2にバンを含めたクイナ科の系統樹を示した。

クイナもバンと同様、水辺に生息するが、めったに泳がない。バンの祖先はクイナのようなものだったと考えられる。ニュージーランドに生息するセイケイも水かきをもたないが、この鳥もよく泳ぐという。バンに近縁なオオバンは、足に水かきに似た弁足と呼ばれるひらひら状のものをつけていて、バンよりも泳ぎがスムーズである。オオバンのほうがバンよりも先に現在のような生活を始めたのかもしれない。ダーウィンによれば、バンのような例は、創造主によって造られたと考えるにはあまりにも完全さからほど遠いというのだ。
生物はみな過去を引きずりながら生きている。生物の進化は、常に祖先のもっていた性質を改変させながら進むものである。いわばあり合わせのもので何とかやっていくのが進化であり、ダーウィンによれば、このような不完全な適応もまた進化の証拠だという。自然選択は常に相対的なものであり、その環境でなんとかやっていけるかどうかが重要なのである。
従って、まったく別の世界から外来種がやって来ると、在来種が簡単に絶滅することがある。これまで実際に遭遇しなかったものに対する備えは、進化しようがないのである。
*もっと「進化」を詳しく知りたい人に最適の本:
長谷川政美著『系統樹をさかのぼって見えてくる進化の歴史』 (ベレ出版)。 本書は当サイトで連載していた「僕たちの祖先をめぐる15億年の旅」を加筆修正および系統樹図を全て作り直して一冊にまとめたものです。カラー図版600点掲載。
扉絵:小田 隆
ブックデザイン:坂野 徹